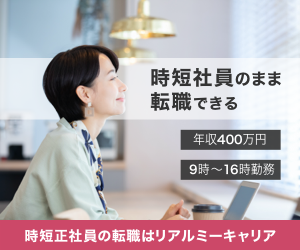小1の壁で退職をすべきかどうかというのは、ワーママにとって非常に悩ましい問題ですよね。
「小学生に上がる時は皆すごく大変だと言う。」「でも会社を一度辞めてしまったら、復職するのが大変そう。」
小1の壁で悩んでいるあなたは、仕事と子育てを天秤にかけた時、「子育て」において後悔をしたくないと思ってるのではないでしょうか。
保育園から小学校へ、上がってからの違いをざっとあげてみます。
- 学校からのお便り・連絡など目を通すものが多い。
- 準備して持たせるものが増える。
- 文房具など消耗品のチェック・補充。
- 学校の交友関係の把握がしずらくなる。
- 毎日宿題の丸付け・音読カードの記入。
- 体操着や上履きの週末の洗濯量。
- 夏期の水筒準備(毎日洗う)。
- 長期休暇の学童のお弁当作り。
- 学校・学童の開始・終了時間に帰宅を合わせる問題。
- 年に数回、朝の旗持ち当番がある。
- その他、学校行事の協力などがある。
※当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
いよいよ小学校では、勉強に運動、交友関係、社会性を学びはじめます。
それらのことに、はじめて経験する過程で、低学年・・少なくとも小1の子には、親のサポートが不可欠だと思います。
けれど、正社員を辞めてしまって良いのか、退職したら後悔ではないのか。
多くのママが悲鳴をあげる小1の壁について、私の2回分の実体験からも赤裸々に紹介していきたいと思います。
また、小学校生活で、小1の壁だけが大変なのかなども書いていますので是非参考にしてみてください。
※小学校にあがるのと同時に時短勤務が切れてしまうのが悩みの場合
最近はワーママに特化した時短正社員専門の転職エージェントがあるのはご存じですか?
リアルミーキャリアは、時短勤務案件、リモート勤務ありの案件をメインに扱う子育て中ワーママ向けの転職エージェントです。
ただし案件が都内及び近郊になるので、都内に通える人なら正社員を続けるために転職活動をしてみるのもひとつの手段だと思います。
小1の壁とは?必ずぶつかるもの?

「小1の壁」というと、ひとつの山のように思えるかもしれませんが、いくつもの山がありました。
小学校は、親自身がやらなければならないことがとても増えると感じました。
小学校に入って間もなく、「めちゃくちゃ大変、保育園に戻りたいよ・・。」と漏らしてるママもいました。
保育園のときの手厚さと小学校にギャップを感じてしまうことが多いのです。
小学校入学式までの春休み問題
小学校入学前の春休み問題が、最初の壁になるかもしれません。
待機児童がいる学童では、入れるかどうかがまずは第一関門に。
入れた場合、保育園へは3月いっぱい、4月1日から入学式前でも小学校の学童へ通わせることが出来ます。
その次には、まだ入学前の小学校の学童への不安かもしれません。
保育園とはガラリと違う雰囲気、小学生の年上の子も混ざって遊ぶことなど、環境が大きく変わるので、大丈夫かな、入学前に学校嫌いになったりしないかな、などと考えたりしました。
実際は、お休みを取ったり祖父母宅に預けたりと、新1年生がほぼいない日もありました。
私の場合、仕事を続けていたら、学童の開始時間よりも先に家を出ないといけない、帰宅後のお迎えもギリギリでした。
また、4月中はまだ4時間授業、昼食後は学童で過ごすことになり、はじめの頃はクラスよりも学童で過ごす時間の方が多いということも気になりました。
うちの子は説明など上手な方じゃなかったので、保育園のように報告もない中、学校での様子を聞いてもよく分からなくて、モヤモヤすることもありました。
いきなり学童で長時間過ごさせる不安というのが、ひとつの山のように感じました。
怒涛の1年生1学期

入学説明会のあと、準備するものを一式そろえ、やっと落ち着いたと思うのもつかの間。
持ち帰るプリントを都度都度見て、用意しなければいけないものが意外とありました。
子供もすっかり忘れていて、「今日牛乳パック使うんだって!」なんて当日の朝に言い出すことも・・。
慣れるまでは子どもも疲れて帰ってくる、家で機嫌が悪くなる、ちょっとしたことで愚図ったりすることもありました。
保育園では時間に縛られない生活だったのに、小学校は長い時間座って過ごす、ルールが多いなど、やはり慣れるまでは疲れるのでしょう。
環境が変わるとき、適応力が高い子、少しかかる子と色々だと思います。
1年生の1学期、親にかかる負担は次のような感じでした。
4月
- 毎日持ち物チェック
- 学校で共同購入したノート、ドリルや学用品などに記名
- 毎週プリントが配布されるため、お知らせ・家庭へのお願いなどを細かく確認
- 子どもが学校生活で疲れて帰ると機嫌が悪い
5月
- 遠足や写生会などの行事の持ち物準備
- そろそろ宿題(親は丸付け・音読チェック)がはじまる
- 運動会を実施する学校もあり更に子供が疲れて帰る
6月
- 6月下旬頃はじまるプールの準備
- 水筒持参がはじまる
- 少し慣れて来たところでトラブルがあったという話も
持ち物は流動的だったりして、その確認もあるので、仕事から帰ってからこなすルーチンは増える覚悟が必要です。
洗いものや準備が想像以上
普段着以外にもなんだかんだで、洗うものが結構増えたことも大変だと感じたことのひとつです。
- 給食のランチョンマット
- 週末は体操着に靴・上履き
- 夏は水着に水筒
- 給食当番の時は白衣
- 習い事があればそのウェア類
わが家はスポーツ系の習い事をやっているのもあって、今は、ほぼ毎日洗濯しています。
上履きは、学童用と2足用意する場合もあります。学校によると思いますが、学童とクラス用と同じ場合は、日々の持ち帰りも少し大変です。
それ以外にももちろん家庭での洗濯物が出てくるので、ためてしまうと週末がつぶれてしまいます・・。
水筒の中身、水泳などがあればプールの準備、アイロンしてあげないといけないものもある、洋服はサイズも大きくなっていくので、日々出る洗濯物も想像以上でした。
小学校低学年くらいの行動は心配も多い

小学生になると色んなことを学んでくるため、大きく変化・成長する1年です。
けれど、まだまだ考え方や行動は、幼児期の延長線上なのだなと思うこともありました。
わが家でも「まさか!?」と思うようなことが何度かありました。実際にあった出来事です。
夏休みが近くなり学校で作ったものや、その他学用品を持ち帰ってきます。
学童登録しているAちゃんは自分の判断で、一度家へ荷物を置きに帰ると、うちの子と一緒に帰ってきてしまいました。
(本当は学童へまっすぐ行かないとダメなのですが)
私はその頃パートをしていたので、家を留守にしていました。
そこでAちゃんは、帰り道のわが家に寄ってしまい30分くらい遊んでしまいました・・。
学童では出欠を取ると「Aちゃんが学童に来ていない」となり、先生たちが近隣を探してしまう事態に。
その後わが家を出て家に荷物を置いて、学童へと戻ったようですが、1時間くらいの間、先生方やAちゃんの親にとってかなり不安な時間だったでしょう・・。
学童にきちんと通っていれば安心ですが、学童以外の子と遊ぶ約束をしてしまったり、その約束を片方の子は忘れていたり、低学年の頃はそんな事もしょっちゅうありました。
小1の壁はいつごろまで続く?
小1の壁とは、親の負担以外にも様々なケースがあると思います。
勉強面、交友関係、習い事、など小学生のうちには色々な経験や成長があり、その中で心配事が出てくることは何度もありました。
習い事は、1年生後半からひとりで行くことが出来るようになりましたが、うっかり持ち物をバッグに入れ忘れてしまい、パート中に泣いて電話してきたことが・・。
自分でなんとか探してみたけど見つからず、遅刻しそうになり、どうしたらよいか分からなくなってしまったようです。
子供の交友関係のトラブル経験もあります。
はじめの頃は緊張感を持っていたのが、小学校に慣れて来たことで今度は調子に乗ってしまう子が出てきました。
わが家が経験したのは、強い男の子グループが出来始めたことです。
自分よりも出来ない子にマウントとったり、それがエスカレートして強い言葉を発するようになっていきました。
何事も社会経験という理解はありますが、気づいてあげられて良かったと思いました。
なかなか忙しくしていると、気づきにくいこともあるでしょう。
学級崩壊も低学年化していますし、自分たちの子供時代とは全く違うということも頭に置いておいた方がいいかもしれません。
小1の壁を前に退職して良かったと思う理由。

小学校入学を前に、退職を選んだり働き方を変えるママは、4人に1人程度いるといいます。
本当に退職したことが正しかったのか?
わたしの結論としては、やはりフルタイムで働くのをやめて、子供といる時間を増やしたのはメリットが大きかったと思います。
宿題をみてあげるのは必要?
宿題は学童でやってこれますが、基本的に丸付けや音読を聞くことは親がやります。
国語の教科書を読む音読の宿題は、ほぼ毎日出るので聞いて音読シートにチェックします。
子供が高学年になって先生から、音読は大切、宿題もきちんとやってる子とやってない子とでは差がついているという話しを聞きました。
返ってきたテスト用紙を確認してあげることも大切だと思います。
やっぱり子供は、学校から帰って親に見てもらえる、話しを聞いてもらえることも一定のモチベーションになると思います。
横について宿題を見てあげる必要はありませんが、宿題やテストをチェックする時間の確保は必要だと思います。
特に男の子にアルアルなのが、ランドセルの奥からぐちゃぐちゃのプリントがたくさん出てきたという事も・・。
成績に困ったら学習塾に入れればいいという話しも聞いたことがありますが、簡単に思える1~2年生の基礎力は3年生の勉強の土台だとも言われています。
学校からの話しを聞いて思うこと
保育園の行事は、親が休みの土日に行われることがほとんどでしたが、小学校の「保護者会」などは平日に行われます。
クラスの雰囲気、頑張ってること、などやっぱり大人目線で子供から聞いているのとは違う話しを聞くことが出来ます。
あと、忙しく働いてるとどうしてもそこまで見れないご家庭もあるようです。
学年主任の先生からも、子育ては学校任せではなく各家庭でもお願いします・・というような話しが出たこともありました。
知り合いのフルタイムママは、チェックが出来ていなく、忘れ物をさせないよう担任から連絡があったけど、共働きなのも理解して欲しいと話していました。
どちらの立場からしても、大変なのは分かります。
しかし、低学年の頃は特に、本人任せでは足りないことも多いので、親のサポートも必要です。
ママに余力がないと、忘れ物をする子供に対しイライラしてしまったり、学校に不満を感じてしまったりするなど、両立することの難しさを傍から見ても感じました。
正社員を退職して大変だと思ったこと
ここまで、我が家や周りであった小1の壁における色々な心配ごと、親の負担などを紹介してきました。
小学生の子供を親としてサポート出来たのは良かったし、退職を後悔はしていないですが、大変だと思ったのはお金のことと再就職のときです。
そういった体験談も紹介しておきたいと思います。
小1の壁で辞めるとお金の面で後悔する?
公立小・中学校の学費はそれほど高くないから、節約したり、何か切り詰めたりすればなんとかなるかな。とも思っていました。
けれど、一般的に小学校6年間でかかるといわれてる費用以外にも、習い事、交際費、レジャー、塾・・など、各家庭によって違うものの、毎月にしてみると思ったより出てしまいました。
洋服や靴などの消耗品も侮れません。
小学生は成長期で、活発に動いたり遊んだりするので、翌年も着れるかなと思って買ったものでも、汚れやダメージが結構あって、買い替えることも多かったです。
交際費も、友達関係を考えると、お誘いは断れないし、一緒にTDLに行きたいなど、中にはお金がかかる事もありました。
けれど無理して仕事を続けて、別の面で負担になるのも辛い、何か方法はないのかと、当時徹底的に調べました。
そして、ライフプランナーに家の収支や保険などを見直してもらい、無駄なものは削り必要なものは取り入れました。
わが家では、その後も5年に一度くらいのタイミングでライフプランナーに見てもらっています。
自分で調べるには、情報が多すぎたり、それが自分の家の家計に合ったものなのか判断することは難しいですが、お金に関する専門的な最新の知識を持っているので、色々聞いてみるとためになります。
保険は今のニーズに合った商品が結構出ていて、掛け捨ての無駄な保険に入ってしまっていたので、貯蓄も兼ねているものに変更できました。
退職を前に、一旦すべて見直してみると、意外と捻出できたり、無駄をなくせたりします。
わが家も相談している「ベビープラネット」は、子育て中の家庭に適した内容でプランナーさんが提案してくれます。
保険、今後の貯蓄方法など、すごくスムーズに話しが出来ておススメです。
退職に踏み切る場合でも、ライフプランの見通しはしっかりとしておくことをお勧めします。
一度辞めたら再就職するのは大変?
私は小学校が少し落ち着いてから、時短派遣などでフレキシブルに働いてきています。
おかげで、学校での心配ごとや、日々のサポートをする余裕もあったため、小学校生活を振り返っても小1の壁で退職したことに後悔はありません。
ですが、仕事を探す時は何度も面接に足を運んだり、働く予定でいた月にはなかなか決まらなくて、その分貯金を崩すことにもなりました。
派遣やパートは融通が効きやすいですが、正社員に比べ不安定だと感じるのも否めません。
けれど、フルタイムで働きながら小1の壁を乗り越えるというのも悩ましい問題です。
フルタイムの場合と1日6~7時間の時短勤務で比較すると、週にすると5~10時間も違ってきますよね。月にすると20時間以上です。
家にひとりで留守番させる心配、宿題を見る時間的な余裕なども、だいぶ変わってくると思います。
最近は時短勤務からのスタートや、リモート可能な会社を紹介してくれるワーママ向け転職エージェントがあり、転職活動のほとんどの部分を面倒見てくれて、しかも無料で利用できます。
時短勤務専門の「リアルミーキャリア」は、扱う会社が一都三県(東京・埼玉・千葉・神奈川)に限られてしまいますが、都内勤務可能なママには今おススメの転職エージェントです。
今の会社を続けるのはキツそう。だけど、忙しくて転職活動する時間がない!というワーママにぴったりです。
共働きで忙しい中でも、LINEで担当者とやりとりが出来るので、空いた時間を有効に使って転職活動が出来そうです。
※登録は1分で完了しますが、求人を紹介してもらうためには電話面談が必要です。
都内以外で勤務エージェントを利用したい人はこちらも見てみて下さいね。
最後に
長々と書いてしまいましたが、小1の壁だけに限定せず子育てをしながら働くのは様々な壁が立ちはだかることもあると思います。
わが家の一例ではありますが、子育てを後悔したくないママ向けに、記憶の限りまとめてみました。
しかし、働いてお金を稼ぐことも大事ではあるし、難しい問題だと思います。
いずれにしても、まだ経験していない事をリアルに伝えることで、参考にして頂き、よい選択・判断が出来るお手伝いになれば幸いです。